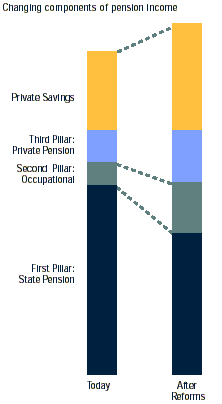Topics 2002年6月21日~30日 前へ 次へ
29日 Lay-offの風景 WorldComの場合
28日 EU企業年金制度の統合
24日 Temporary Workerと経営戦略
21日 生産性を高める戦略
29日 Lay-offの風景 WorldComの場合 Source : WorldCom Lays Off 17,000 Workers (Washington Post)
28日、ついに、WorldComのlay offが始まった。予てから、大規模なlay offが予想されていたが、その規模は、17,000人、全世界の従業員80,000人の約21%にあたる。
上記記事から、lay off当日の模様を再現すると次のようになる。
○28日朝 通常通りの始業
○11時頃 Lay off対象者に、e-mailによる通知が届く
○Lay off対象者は、集会所に集められ、数種類の書類を手渡されるとともに、個人的な所有物の持ち出し方を指示された。
Lay off対象者の心配事は、3つある。第1は、再就職活動だ。Virginia州では、1,300人が対象者となったため、彼らの再就職活動を支援するため、下院議員Frank R. Wolf (R-Va.)とThomas M. Davis III (R-Va.) の二人は、1ヶ月以内にVirginia州北部での就職フェアを開催するための準備を開始した(選挙活動の一環か?)。Laid-offにとって事態が深刻なのは、通信事業全体が不景気であり、laid-off同士が、再就職活動の際に互いが競争相手になることが予想されることだ。
第2の懸念は、severance payment(離職手当)だ。WorldComには、severance paymentの規定があったようだが、これが規定通り支払われるかどうかが、懸念の種となっている。Severance paymentは、公的な失業手当と並んで、失業中の大切な所得である。
これに関し、連邦地方裁判所は、28日、WorldComの財務関係の書類の破棄を禁じると同時に、役職者や財務・会計関係の部署の職員に対して、10万ドル以上の特別手当を支払う事を禁じた。10万ドルの上限に達するようなseverance paymentやretaining bonusをもらうような一般従業員はそうそういないだろうが、少なくとも特定の役職者だけが恩恵にあずかるような手当の支払が行われる事は防げるだろう。また、報道によれば、このような裁判所の命令が出される事は稀であり、Enronの教訓が一つ生かされたということだろう。
話はちょっとそれるが、連邦地方裁判所は、Bernard J. Ebbers (Chief Executive of WorldCom Inc.) 氏の離職手当(150万ドル/年(終身))(Topics 「6月7日 企業トップの離職手当て」を参照)についても、メスを入れてくると見られている。これもEnron事件の教訓と言えるだろう。
そして、第3に、懸念ではなく、現実の問題となってしまったのが、企業年金である。WorldComの事件は、Enronと似た所が多い。会計を不正に操作していたこと(※)、しかも監査法人がArthur Andersenだったこと(今年初めにKPMGに切り替えられている)、過去に買収を繰り返して大きくなってきていること、等々が挙げられる。
WorldComの企業年金全体がどうなっていたのかはまだよく調べてはいないが、確定拠出型(DC)の制度(401(k))を持っており、そこでは、かなりの割合で自社株に投資されていたようだ。Enronの場合と同様、WorldComの従業員の退職金がほとんどパーになったケースも紹介されている(USA Today)。
ただし、Enronの場合と違うのは、①Black Out(Topics 「2月1日 401(k)プラン改革 大統領提案」参照)がなかったこと、②自社株への強制投資がなかったこと、である。しかし、②にもかかわらず、多くの従業員は、自社株に投資していたのは、やむを得ない。会社と(おそらくは)会計監査がぐるになって、嘘の財務報告書を出していれば、それを見抜けというのが無理だろう。
こうした企業年金の損失の責任を追及するため、27日には、Seattleに本拠を置くKeller Rohrback L.L.P.が、クラスアクションを起こした。この法律事務所は、Enronのケースについても、共同訴訟人となっている。同事務所が起こしたWorldComに対する告訴では、401(k)運営責任者が、受益者に対する忠実義務を怠り、投資においてプルーデントマンルールを守っていなかったとして、受託者責任を追及している。これはEnronのケースと同じで、経営者としての立場と年金運営者の立場の間に利益相反が起きているという訳だ(Topics 「2月18日 経営者の受託者責任」参照)。
WorldComの場合は、Enronの場合よりも従業員の恨みを買っているという印象だ。特に、旧MCIの職員は、WorldComに買収されてから、会社の雰囲気が悪くなったと嘆いているらしい。
アメリカ企業は、企業会計に対する不信感と企業年金に対する不安感を払拭するために、しばらく戦わなければならなくなったようだ。
ところで、Washington Wizardsは、来シーズン、MCI Centerでプレイできるのでしょうか?
28日 EU企業年金制度の統合
Source : One Europe, One Pension (European Financial Services Round Table)
Topicsの「6月14日 EUの企業年金」で、EU域内での企業年金のポータビリティが検討されているという、Financial Timesの記事を紹介した。上記Sourceは、6月27日に、European Financial Services Round Table(EFS)という、EUの金融機関の団体が公表した提言で、ポータビリティだけでなく、企業年金制度全体の統合を求めている。
この提言の要旨をまとめると、次のようになる。
①EU域内の公的年金は、長寿化と出生率低下から、危機に直面している。現在の現役労働者/年金受給者の比率は2.6だが、2040年には1.4となる。公的年金の早急な改革とともに、EUにおける統一された第2の年金(企業年金)、第3の年金(個人年金)を育てていく必要がある。
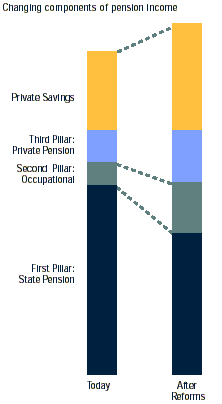
②EU域内で労働者が自由に移動できるようにすることは、労働者の権利であり、企業にとっても好ましいことである。
③まず、各国の年金税制を、EETシステムに統合する必要がある。
(注:EETとは、"pension contributions are Exempt
(E), where funds are Exempt (E) during the accumulation stage, and where the proceeds of pension funds are Taxed (T)"、つまり給付時課税の原則のこと。)
④個人が、国の間を移動したり、年金運営管理会社を変更したりすることができるようにする。
⑤企業が、EU全域で、一つの企業年金制度を適用できるようにする。
⑥現時点での年金給付額の情報を従業員に提供できるようにする。
⑦プルーデントマン・ルールに基づいた規則を設ける 等々。
日本にとっての示唆は2点ある。第1は、企業年金制度はもちろん、労働政策全般について、労働の移動を可能とすることを前提にした体系に組み替えていく必要があるということだ。確定拠出年金制度は始まったものの、その他の制度、基盤の整備がまだまだ遅れている。EUも決して速いとは思えないが、現実に、EU域内で労働者が移動し始めており、企業側もそれを視野にいれた経営をし始めているのだ。世界の企業活動にとって、有能な人材(人財)は貴重かつなかなか得がたい資源である。それを有効に活用できる企業、地域が、勝ち組になることは明らかだ。公的年金だけでなく、企業年金までを視野に入れたEUの動きは、警戒すべきであり、日本も遅れてはならない。
第2は、税制の国際的調和である。EU各国の企業年金税制は次のようになっている。

これを見る限り、確かに課税システムはEETが有力だが、G8メンバーである、ドイツ、イタリアが異なるシステムとなっている。長く続いてきた税制を転換するのは大変困難な課題だが、この提言がトップ・プライオリティを置いているように、年金制度における税制は大変重要だ。税制の違いを放置しておけば、二重課税が発生し、事実上国の間の移動はできなくなる。
日本でも、経済財政諮問会議のイニシアティブで、受給時課税の原則が導入されようとしている。その際、日本の年金税制で課題となるのが、特別法人税と公的年金等控除だ。特に、特別法人税は、確定給付型でも確定拠出型でも、ファンドが累積しているところに、1.173%をかけようという税制で、年金の世界ではすこぶる評判が悪い。これでは、ファンド積立の抑制効果しかないからだ。現時点では、景気対策ということで、特別措置で課税が停止されているが、いつ復活されるかわからない。こんな悪税は早急に廃止すべきだ。
しかし、既に税制の良し悪しを議論している段階ではなくなっている。世界の主要な経済地域が採用しようとしているEETに変更しておかなければ、日本にやってくる、またはとどまる人財は、いなくなるのだ。
(おまけ)最近、こんな所に行ってきました。
24日 Temporary Workerと経営戦略 Source : A Workforce Divided (Washington Post)
アメリカの雇用形態の中で、Templorary workerの割合が増えている。10年前には、100万人程度で全体の1%弱しかなかったのが、現在では、290万人、全体の約2.5%に達している。
日本でも同様の動きが出ているので、その理由はよく理解できると思うが、第1は、専門知識を有する人材を活用しやすい形態であること。第2は、雇用数を需要の増減に合わせて変動させやすいことである。
上記記事では、その第2の要因について詳しくレポートしている。簡単にまとめてしまえば、在庫管理の考え方である"just-in-time"の手法を、雇用にも当てはめ、コスト管理をしようというわけである。まさに、雇用を変動費としてとらえようとしているわけだ。
企業経営側から見ると、やはり正社員の解雇は、辛いものである上に、社会的にも白い目で見られるし、残った社員の士気にも影響する。しかし、Temporary workerなら、もともとそういう性格の雇用形態なのだから、減らしやすいという意識があるようだ。
しかし、templorary worker側から見ると、そのような雇用形態により、希望の企業に勤めるチャンスを得られる可能性があることを評価しつつも、長年同じ企業にtemporary workerで働けば、いつかは正社員にしてもらえるという望みは強い。上記記事によれば、2000年の連邦最高裁判決では、長年Microsoft社に勤めたtemporary worker達の訴えを認め、正社員と同様のbenefitを与えるべきとの判断を下した。
この判決は、一見、temporary workerにとって朗報のように見えるが、実は、企業がtemporary workerの契約を短くすることにつながるため、本当にtemporary workerにとってメリットとなるか、疑問である。実際、日本の労働者派遣法では、当初、継続して一定期間同じ職場に派遣されていると正社員として採用しなければならない、としていたため、その法定期間が事実上継続期間の天井として認識されてしまい、その前に企業側が継続を打ちきるということになった。
私はこの記事を読んでいて、3つ感じた点があった。
第1は、temporary workerの増加により、雇用の柔軟性を確保しようとしているアメリカ企業経営者に、あくまでも"Employment at will"を遂行しようとしている意思を窺い知ることができる。確かに、現在では、handbook等で、『いつ何時でも理由の有無に関わらず、雇用関係を終了することができる』と、企業側の雇用関係における裁量権を確保しようとしているが、まだまだ社会文化的には、完全に受容されていないところがある。従って、最初から割り切った形で雇用契約を結ぶtemporary workerという形態を増やし、柔軟性を確保しようというのだろう。
第2は、temporary workerの増加により、資源配分の適正化のテンポが速まる、ということだ。派遣社員というのは、もちろん景気循環に伴う雇用の増減が多くなりやすい。この点では、確かに上記記事が指摘しているように、派遣社員の職を不安定にする。しかし、景気循環を超えた構造的変化への対応を考えたとき、長期的に派遣社員を増やそうという企業、産業は、成長企業・産業であり、構造不況業種ではないはずだ。そう考えれば、temporary workerにとって、収入が高まるチャンスが増すとも言えるのではないか。
第3に、アメリカ企業がtemporary workerを増やしていけるのは、そのベースに、job descriptionが一般化しているからだ。上記記事でも、最初は、temporary workingはシリコンバレーから定着していったと書いている。それは、IT分野には、個々の企業の文化と無関係に仕事を進められる部分が多くあったためだ。しかし、現在では、それが企業全般に広がっている。それを可能としているのが、job descriptionだと思う。これがあれば、temporary workerは、企業文化を理解していなくても、遂行すべき業務がある程度把握できる。あとは経営者、managerがそれらをコーディネイトすればよい。
日本の労働市場の現状を考えると、やはり最後の点の、job descriptionが遅れている事に不安を覚えざるを得ない。
21日 生産性を高める戦略
Source : For Companies Eager to Boost Productivity, the Time to Act is Now (AON)
このレポートは、人事関係のコンサルティングファームであるAONと、雇用問題に関する研究を進めているペンシルバニア大学Wharton Schoolの教授陣との共同研究の成果である。企業の人事戦略について、コンサルティング会社と大学が研究レポートを出すなんて、日本ではまったく想像もつかないが、それがアメリカの現実だ。どちらもアメリカ企業の内部まで深く入り込み、企業と共存関係にある。
さて、そのレポートの中身だが、景気が上向きかけた今こそが生産性向上のための改革を実践する絶好のチャンスであり、ITを使った人事制度改革が効果的だとしている。以下、レポートの主な概要を箇条書きにしておく。
① 世界経済の成長が鈍化している中、企業の人事戦略の重点は、新たな有能な人材の確保ではなく、現存する従業員の仕事の効率を最大限に高めることにある。
② Wharton SchoolのPeter Cappelli教授は、景気後退から上昇に向かい始める時が、生産性向上のための改革を行うチャンスだと主張する。なぜなら、仕事のやり方を変えられるので、その効果が長続きするからだ。
③ かつて、生産性とは、一人あたりの生産量と考えられてきたが、現在では、投入一単位あたりの生産量として定義されている。昔の考え方では、従業員がたくさん働けば、生産性は向上した。しかし、それでは、労働コストもかさむことになるため、必ずしも生産性が上がるとは言えない。現在の定義では、生産性向上のためには、効率よく働くことが重要になる。
④ 様々な研究の結果、製造業でもサービス業でも、意思決定に従業員が参加すること、従業員により広い責任を持たせることで、生産性が向上していることがわかっている。
⑤ 人材への投資と技術への投資がうまくかみ合った時に、生産性は大きく向上する。例えば、アメリカの大企業527社を対象にした調査では、短期で見ると、コンピュータ化により生産量は増加したが、生産性は向上しなかった。ところが、長期で見ると、生産性の向上は5倍にもなることがわかった。その理由は簡単で、コンピュータの導入により、人手が機械化されるだけではなく、仕事のやり方、組織がすべて見直されるからだ。逆に言えば、コンピュータの導入と組織改革、人事制度改革が並行して行われなければ、その効果は限られたものになる。
⑥ "Presenteeism"に対処できなければ、長期的に見た生産性の向上は難しい。presenteeismとは、新語で、雇用されてはいるものの、ストレスや病気、怪我のために、生産性の高くない従業員の症状を指している。イギリスでは、過度に働きすぎる従業員を指すこともある。どちらも同じ現象の表裏であり、このような現象は、職を失うことへの不安から来ている。Presenteeismを回避するためには、従業員が職場と家庭のバランスを取れるように配慮しなければならない。どちらかが不安定になると、相乗効果が生じて、いずれは仕事の生産性に影響を及ぼし、absenteeismにつながる。
⑦ 雇用関係にありながら従業員が職場に出てこない状態を、absenteeismと呼ぶ。その理由は様々で、病気、FMLA("Family and Medical Leave Act"。子供の出産、家族の病気、本人の病気などのために、一定期間無給で休暇を取得することができる。)、障害、労災、転職など。多くの企業は、それぞれについて、別々のセクションが対応している。例えば、労災は危機管理部門、障害は人事部門、FMLAは法務部門、というように。これらを統合して管理するだけで、相当のコスト削減となる。
私は、特に③と⑤に注目したい。「一所懸命やれば報われる」というのは、もういい加減にしないといけない。労働は、趣味や勉強とは異なる。「市場」という世界の重要な構成要素である。それを努力や労働時間だけで評価するようでは、全体の資源配分が歪んでしまう。また、⑤も耳の痛い話だ。会社から支給されているPCが、単なるワープロとなっていないか、内線電話の代わりになっていないか、ということだ。
The Gateway to the US Labor Marketに戻る